【2025年最新版】請求書受領サービス比較10選!選び方の完全ガイド
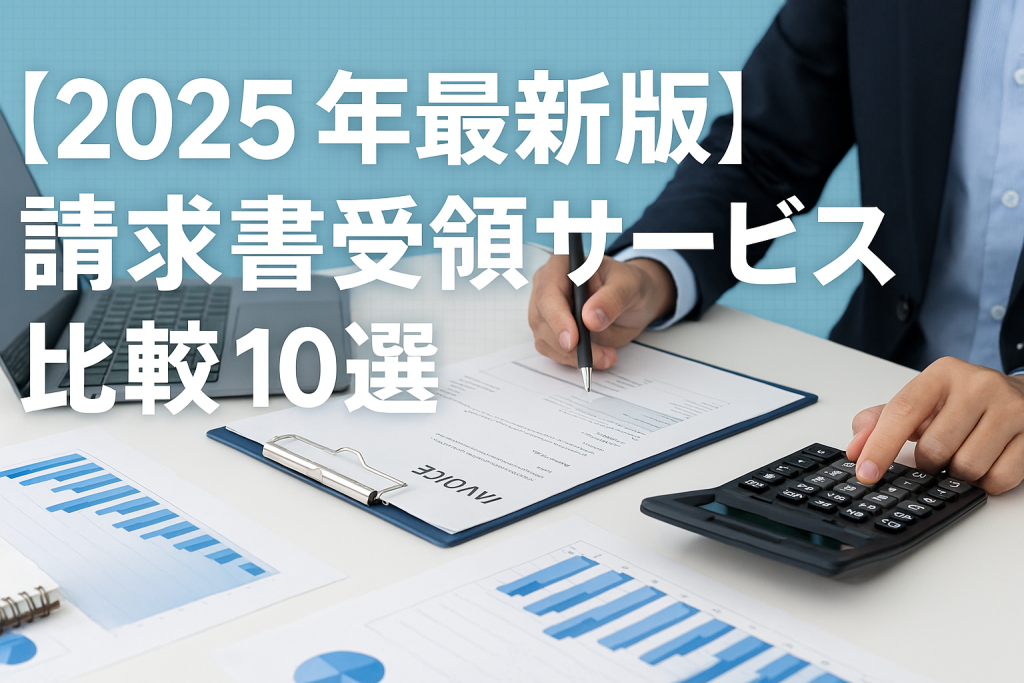
はじめに
請求書処理業務の効率化は、多くの企業にとって喫緊の課題です。日々大量に発生する請求書の受け取り、確認、入力、承認、保管といった一連の作業は、手作業に頼ると膨大な時間とコストを要し、人的ミスの温床ともなりかねません。このような課題を解決する切り札として、「請求書受領サービス」が注目を集めています。しかし、市場には多種多様なサービスが存在し、「どのサービスを選べば自社に最適なのか分からない」という声も少なくありません。
本記事では、2025年最新の情報に基づき、主要な請求書受領サービスを10種類厳選して徹底比較します。各サービスの機能、料金体系、サポート体制、得意とする分野などを多角的に分析し、読者の皆様が自社の規模や業種、特有のニーズに最適なサービスを選び抜くための「完全ガイド」となることを目指します。さらに、サービス選定で失敗しないための重要なチェックポイントや、ファーストアカウンティングが提供するソリューションについても触れながら、請求書受領サービス導入による業務改革を成功に導くための実践的な情報を提供してまいります。
第1章:請求書受領サービス選定の重要性と基本的な考え方
請求書受領サービスは、一度導入すると業務プロセスに大きな影響を与えるため、その選定は慎重に行う必要があります。安易な選択は、期待した効果が得られないばかりか、かえって業務の混乱を招く可能性すらあります。ここでは、サービス選定の重要性と、選定にあたっての基本的な考え方を整理します。
なぜ慎重なサービス選定が必要なのか?
- 業務への影響範囲の広さ: 請求書処理は経理部門だけでなく、購買部門、営業部門、そして承認者である各部門長など、社内の多くの関係者と関わります。新しいサービスの導入は、これらの関係者全員の業務フローに影響を与えるため、慎重な検討が不可欠です。
- 投資対効果(ROI)の最大化: 請求書受領サービスの導入には、初期費用や月額利用料といったコストが発生します。投資に見合うだけの効果(業務効率化、コスト削減、ミス削減など)を得るためには、自社の課題解決に直結する機能を備えたサービスを選ぶ必要があります。
- データ移行と定着化のコスト: 既存の業務プロセスから新しいシステムへ移行するには、データの移行作業や従業員への教育・トレーニングが必要です。選定を誤ると、これらのコストが無駄になるばかりか、従業員のモチベーション低下にも繋がりかねません。
- 法制度対応の確実性: 電子帳簿保存法やインボイス制度など、関連する法制度への対応は必須です。選定するサービスがこれらの法制度に適切に対応しているかを確認することは、コンプライアンス遵守の観点からも極めて重要です。
選定における基本的な考え方
最適なサービスを選ぶためには、まず自社の現状とニーズを正確に把握することが出発点となります。
- 現状の課題分析: 現在の請求書処理業務において、具体的にどのような点に課題を感じているのか(例:処理時間、コスト、ミス、保管スペース、テレワーク対応の遅れなど)を明確にします。
- 導入目的の明確化: サービス導入によって何を達成したいのか(例:処理時間を50%削減、ペーパーレス化率80%達成、月次決算の3日早期化など)具体的な目標を設定します。
- 必須要件と希望要件の整理: サービスに求める機能を「絶対に譲れない必須要件」と「あれば望ましい希望要件」に分けて整理します。これにより、比較検討の軸が明確になります。
- 予算と導入時期の決定: 導入にかけられる予算の上限と、いつまでに導入を完了したいかというスケジュールを設定します。
- 将来の拡張性の考慮: 現時点でのニーズだけでなく、将来的な事業規模の拡大や業務内容の変化にも対応できる拡張性があるかどうかも考慮に入れておくと良いでしょう。
これらの基本的な考え方に基づき、次章以降で紹介する具体的な比較ポイントやサービス情報を参考に、自社にとって最適な一社を見つけ出してください。
第2章:請求書受領サービス比較の重要チェックポイント
数ある請求書受領サービスの中から最適なものを選ぶためには、いくつかの重要なチェックポイントがあります。ここでは、特に比較検討すべき項目を5つに絞って解説します。
チェックポイント1:データ化の精度と範囲(AI-OCRの性能)
請求書受領サービスの核となる機能の一つが、AI-OCRによる請求書情報のデータ化です。この精度と、どこまでの情報をデータ化できるかが、業務効率に直結します。
- 読み取り精度: 請求書番号、発行日、取引先名、品目、数量、単価、金額、税区分、支払期日など、必要な項目をどれだけ正確に読み取れるか。特に、手書き文字や多様なフォーマット、印影が重なった文字など、読み取りが難しいとされるケースでの精度を確認しましょう。多くのサービスが無料トライアルを提供しているので、実際に自社の請求書で試してみるのが最も確実です。
- 対応フォーマット: 紙の請求書(スキャン)、PDF(テキストPDF、画像PDF)、FAX、電子請求書など、自社が受け取る可能性のあるあらゆる形式の請求書に対応しているか。
- データ化項目: 基本的な項目以外に、明細単位でのデータ化、摘要欄の読み取り、振込先口座情報の読み取りなど、どこまで詳細にデータ化できるか。自社の仕訳や分析に必要な情報が網羅されているかを確認します。
- 学習機能の有無: AI-OCRが、読み取り結果の修正を通じて学習し、使えば使うほど精度が向上する機能があるか。これにより、特定の取引先やフォーマットへの対応力が強化されます。
チェックポイント2:機能の充実度(ワークフロー、会計システム連携など)
データ化された情報をどのように処理し、既存システムと連携できるかも重要なポイントです。
- 承認ワークフロー: 請求金額や部門に応じて承認ルートを自動で分岐させたり、代理承認や差戻しといった柔軟な設定が可能か。スマートフォンやタブレットからの承認に対応しているかも確認しましょう。
- 会計システム連携: 利用中の会計システムやERPシステムとスムーズに連携できるか。API連携、CSVファイル連携など、連携方法の種類と設定の容易さを確認します。自動仕訳機能や勘定科目の自動提案機能があれば、さらに効率化が進みます。
- 検索・保管機能: 電子帳簿保存法の要件を満たす形で、長期間安全にデータを保管できるか。検索項目(取引先名、日付、金額など)の豊富さや、検索スピードも重要です。
- インボイス制度対応: 適格請求書発行事業者の登録番号の照合機能、税率ごとの金額集計機能など、インボイス制度への対応機能が充実しているか。
- その他便利機能: 発注書や納品書との突合機能、支払予定表の自動作成機能、督促アラート機能など、業務を補助する付加機能も比較検討の対象となります。
チェックポイント3:料金体系とコストパフォーマンス
サービスの料金体系は、初期費用、月額基本料金、従量課金(処理枚数やユーザー数に応じた課金)など様々です。自社の利用規模や予算と照らし合わせて、最適なプランを選ぶ必要があります。
- 初期費用: システム導入にかかる初期設定費用やコンサルティング費用など。
- 月額基本料金: 基本機能を利用するための固定費用。含まれる処理枚数やユーザー数に上限がある場合が多いです。
- 従量課金: 基本料金に含まれる上限を超えた場合に発生する追加料金。1枚あたりの単価や、1ユーザーあたりの単価などを確認します。
- オプション料金: 特定の機能(例:高度なワークフロー、特定のシステム連携モジュールなど)を利用する場合の追加料金。
- 最低利用期間と解約条件: 契約期間の縛りや、解約時の違約金などについても事前に確認しておきましょう。
単純な料金の安さだけでなく、提供される機能やサポート内容を総合的に評価し、コストパフォーマンスの高いサービスを選ぶことが重要です。
チェックポイント4:サポート体制と導入実績
新しいシステムをスムーズに導入し、安定して運用するためには、サービス提供事業者のサポート体制が不可欠です。
- 導入サポート: 導入計画の策定支援、初期設定代行、操作トレーニングなど、導入フェーズでのサポート内容。
- 運用サポート: 電話、メール、チャットなど、問い合わせ方法の種類と対応時間。FAQやオンラインマニュアルの充実度も確認しましょう。
- 障害対応: システム障害発生時の対応フローや復旧までの時間。
- 導入実績: 同業種や同規模の企業への導入実績が豊富であれば、自社の課題やニーズに対する理解が深く、スムーズな導入が期待できます。具体的な導入事例や顧客の声も参考にしましょう。
- セキュリティ体制: データの暗号化、アクセス制御、バックアップ体制、情報セキュリティ認証(ISO27001など)の取得状況など、セキュリティ対策が万全であるかを確認します。
チェックポイント5:操作性とカスタマイズ性
実際にシステムを利用する経理担当者にとって、直感的で分かりやすい操作画面であることは非常に重要です。また、自社の業務フローに合わせてある程度のカスタマイズが可能かどうかも確認しておきたいポイントです。
- ユーザーインターフェース(UI): 画面が見やすいか、操作に迷うことがないか。無料トライアルやデモで実際に触れて確認するのが最も効果的です。
- ユーザーエクスペリエンス(UX): 一連の操作がスムーズに行えるか、ストレスなく利用できるか。
- カスタマイズ性: ワークフローの承認段階や承認条件、表示項目、帳票レイアウトなど、自社の運用に合わせてどの程度柔軟に設定変更が可能か。
- モバイル対応: スマートフォンやタブレットからも主要な機能(承認、閲覧など)が利用できるか。テレワークや外出先での利用を想定している場合は必須の確認項目です。
これらのチェックポイントを参考に、自社の優先順位を考慮しながら、複数のサービスを比較検討していくことが、最適なサービス選定への近道となります。
第3章:【2025年最新】請求書受領サービス比較10選
ここでは、現在市場で注目されている請求書受領サービスの中から、特に評価の高い10サービスをピックアップし、それぞれの特徴、強み、料金目安などを比較形式でご紹介します。自社のニーズと照らし合わせながら、最適なサービスを見つけるための一助としてください。
(注:以下に示すサービス内容や料金は、2025年5月現在の一般的な情報に基づいたものであり、変更される可能性があります。最新かつ詳細な情報は、各サービスの公式サイトで必ずご確認ください。)
| サービス名 | 提供会社 | 特徴・強み | 料金目安(月額) | AI-OCR精度 | 会計連携 | おすすめ企業規模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファーストアカウンティング スキャンセンター | ファーストアカウンティング株式会社 | 受領代行「Remotaスキャンセンター」。高精度AI-OCR「Remota」と証憑処理AI「Robota」で請求書処理を自動化。柔軟なカスタマイズとシステム連携。電子帳簿保存法・インボイス制度対応。 | 要問い合わせ | ◎ | ◎ | 中堅~大企業 |
| ハーモス経費 | 株式会社ビズリーチ | 高精度AI-OCRで明細行まで瞬時に読み取り。請求書受領だけでなく、請求書発行・経費精算・ワークフローまで1つのシステムで完結。 | 29,000円〜 | ◎ | ◎ | 中小企業〜大企業 |
| TOKIUMインボイス | TOKIUM株式会社 | 請求書の受領代行からデータ化、承認、保管まで一気通貫。オペレーターによる二重チェック | 要問い合わせ | ◎ | ◎ | 中堅~大企業 |
| Bill One | Sansan株式会社 | オンラインで受領・データ化。名刺管理で培ったAI技術とオペレーター入力。 | 要問い合わせ | ◎ | 〇 | 全規模 |
| マネーフォワード クラウド債務支払 | 株式会社マネーフォワード | 請求書の受領・データ化から支払処理、仕訳連携まで自動化。AI-OCRとオペレーター入力。 | 5,000円~ | 〇 | ◎ | 中小~中堅企業 |
| バクラク請求書受取 | 株式会社LayerX | AI-OCRによる高精度な自動読み取りと仕訳推測。 | 30,000円~ | ◎ | ◎ | 中小~中堅企業 |
| invox受取請求書 | 株式会社invox | AI-OCR+オペレーター。安価な料金設定。 | 980円~ | ◎ | 〇 | 小規模~中小企業 |
| freee会計(請求書処理機能) | freee株式会社 | 会計ソフト一体型。請求書の取り込み、AI-OCRによるデータ化、仕訳、支払管理 | 1,980円~ | 〇 | ◎ | 小規模~中小企業 |
| Concur Invoice | 株式会社コンカー | 経費精算システム「Concur Expense」と連携し経費精算を一元管理。グローバル対応。 | 要問い合わせ | 〇 | ◎ | 中堅~大企業 |
| BtoBプラットフォーム請求書 | 株式会社インフォマート | 発行・受取双方で利用可能。取引先も利用することで請求書の電子化を推進。 | 5,000円~ | 〇 | 〇 | 全規模 |
凡例:
- AI-OCR精度: ◎:非常に高い / 〇:高い
- 会計連携: ◎:多様なシステムと容易に連携可能 / 〇:主要システムと連携可能
- サポート体制: ◎:非常に充実 / 〇:充実
- タイプ: 受領代行型、システム提供型、プラットフォーム型など
第4章:自社に最適な請求書受領サービスの選び方・完全ガイド
前章で紹介したサービス以外にも、市場には多くの請求書受領サービスが存在します。その中から自社にとって本当に最適なサービスを選ぶためには、体系的なアプローチが必要です。ここでは、具体的な選定ステップと、各ステップでのポイントを解説します。
ステップ1:現状課題の徹底的な洗い出しと目標設定
- 業務フローの可視化: まず、現在の請求書受領から支払までの業務フローを詳細に書き出し、各プロセスで「誰が」「何を」「どれくらいの時間とコストをかけて」行っているかを可視化します。
- 課題の特定と数値化: ボトルネックとなっている箇所、ミスの発生しやすい箇所、時間がかかりすぎている箇所などを特定し、可能であれば課題を数値化します(例:月間処理枚数、平均処理時間、ミス発生件数、残業時間など)。
- 導入目的の明確化とKGI/KPI設定: サービス導入によって何を達成したいのか(KGI:重要目標達成指標)を明確にし、それを測定するための具体的な指標(KPI:重要業績評価指標)を設定します(例:KGI「月次決算の3日短縮」、KPI「請求書処理時間を50%削減」「データ入力ミス0件」)。
ステップ2:必須要件と希望要件のリストアップ
洗い出した課題と設定した目標に基づき、新しいサービスに求める機能を「必須要件(Must-have)」と「希望要件(Want-to-have)」に分類してリストアップします。
- 必須要件の例: 電子帳簿保存法・インボイス制度への完全対応、AI-OCRによる99%以上のデータ化精度、主要会計システムとのAPI連携、柔軟な承認ワークフロー設定、堅牢なセキュリティ体制など。
- 希望要件の例: スマートフォンアプリ対応、多言語対応、発注書との自動突合機能、過去データの分析機能、チャットボットによるサポートなど。
このリストが、サービス比較検討の際の評価基準となります。
ステップ3:情報収集と比較検討(RFI/RFPの活用)
リストアップした要件をもとに、候補となるサービス提供事業者に対して情報提供依頼(RFI:Request for Information)や提案依頼(RFP:Request for Proposal)を行います。
- 情報収集: 各社のウェブサイト、製品カタログ、導入事例、第三者機関による評価レポートなどを収集します。
- 比較表の作成: 収集した情報やRFPへの回答をもとに、機能、料金、サポート体制、セキュリティなどを一覧できる比較表を作成します。第3章の比較表も参考にしてください。
- ショートリストの作成: 比較表と必須要件を照らし合わせ、候補を3~5社程度に絞り込みます(ショートリスト)。
ステップ4:デモンストレーションと無料トライアルの実施
ショートリストに残ったサービスについては、必ずデモンストレーションを依頼し、可能であれば無料トライアルを実施して、実際の操作性や機能を体験します。
- デモンストレーション: 自社の業務フローや課題を事前に伝え、それに合わせたデモを依頼します。疑問点はその場で質問し、解消しましょう。
- 無料トライアル: 実際に自社で日常的に受け取っている請求書(様々なフォーマット、手書き、印影が濃いものなど)を使って、AI-OCRの読み取り精度やデータ化のスピード、操作性を評価します。複数の担当者で試用し、フィードバックを集めるのが理想です。
ステップ5:最終評価とサービス決定
デモやトライアルの結果、および提供事業者との質疑応答を通じて得られた情報を総合的に評価し、最終的に導入するサービスを決定します。
- 評価基準の再確認: ステップ2で作成した必須要件・希望要件リストと照らし合わせ、各サービスがどの程度要件を満たしているかを客観的に評価します。
- コストパフォーマンスの評価: 単純な価格だけでなく、機能、サポート、将来性などを総合的に考慮し、最もコストパフォーマンスが高いと判断できるサービスを選びます。
- 導入パートナーとしての信頼性: 長期的な視点で、信頼できるパートナーとなり得るかどうかも重要な判断材料です。企業の安定性や開発力、サポートの質などを考慮しましょう。
- 社内合意の形成: 選定理由や導入効果などを関係者に説明し、社内での合意を形成します。
第5章:ファーストアカウンティングのソリューションが選ばれる理由
多くの請求書受領サービスが存在する中で、ファーストアカウンティングのソリューション(Remota スキャンセンター、AI-OCRエンジン「Remota」、証憑処理AI「Robota」)がお客様に選ばれる理由は何でしょうか。それは、単なる業務効率化に留まらない、経理DXの実現に向けた独自の強みにあります。
1. 業界トップクラスのAI-OCR精度と継続的な進化
ファーストアカウンティングのAI-OCRエンジン「Remota」は、長年の研究開発によって培われた独自のAI技術により、多様なフォーマットの請求書や読み取りが難しいとされる手書き文字、複雑な表形式の明細なども高精度にデータ化します。さらに、お客様からのフィードバックや最新のAI研究成果を常に取り入れ、日々その精度を進化させています。これにより、導入後の運用負荷を大幅に軽減し、信頼性の高いデータ活用を実現します。
2. 柔軟なカスタマイズ性とシステム連携力
企業ごとに異なる業務フローや既存システム環境に対して、柔軟に対応できるカスタマイズ性とシステム連携力がファーストアカウンティングの大きな特徴です。標準機能でカバーできない要件に対しても、お客様のニーズに合わせた個別の機能開発や、特殊な会計システム・ERPとの連携実績も豊富です。これにより、画一的なサービスでは実現できない、真に自社にフィットした請求書処理プロセスの構築を可能にします。
3. 請求書処理に留まらない、経理業務全体のDX支援
ファーストアカウンティングのソリューションは、請求書の受領・データ化だけでなく、その後の仕訳生成、消込作業、支払処理、さらには予算実績管理や経営分析といった、より高度な経理財務業務の自動化・高度化までを見据えています。証憑処理AI「Robota」との連携により、経理部門が定型業務から解放され、より戦略的な業務に注力できる「戦略経理」への変革をサポートします。
4. 専門知識豊富なコンサルタントによる手厚いサポート
導入検討段階の課題ヒアリングから、要件定義、システム設計、導入支援、そして運用開始後のフォローアップに至るまで、経理業務とAI技術の両方に精通した専門コンサルタントが一貫して手厚くサポートします。お客様の「経理DXパートナー」として、システム導入の成功だけでなく、その先の業務改革の実現まで伴走します。
まとめ
本記事では、2025年最新情報に基づき、請求書受領サービスの比較検討から最適なサービスの選び方までを網羅的に解説しました。市場には多種多様なサービスが存在しますが、重要なのは、自社の課題と目的を明確にし、機能、料金、サポート体制などを総合的に比較検討することです。そして、無料トライアルなどを活用して実際の使用感を確かめることが、失敗しないサービス選定の鍵となります。
請求書受領サービスの導入は、単なる業務効率化ツールとしてだけでなく、ペーパーレス化の推進、テレワーク対応、内部統制強化、そして法制度への的確な対応といった、現代企業が抱える多くの経営課題を解決するポテンシャルを秘めています。この機会に、自社の請求書処理業務を見直し、最適な請求書受領サービスの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
ファーストアカウンティングは、業界をリードするAI技術と、お客様に寄り添ったコンサルティング力で、皆様の請求書処理業務の変革、そしてその先の「戦略経理」の実現を全力でサポートいたします。ご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。